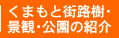|
■巨大な幹のクスノキ
JR三角(みすみ)線の住吉駅のすぐ西を流れる網津(あみづ)川沿いの道を南に、有明海の海岸線と直角の方向に1.5キロメートルほど進むと、右手に馬門(まかど)の集落が見えてきます。集落に入ってすぐ右側に大歳神社があり、その社殿の裏側にこのクスノキがあります。神社の正面から見ると、社殿の裏に2本の樹がそびえているように見えますが、実際は1本の樹の枝が斜め上の方向に伸びて、それぞれ別の樹のように見せているのです。
社殿の裏に回って見ると、主幹が枯れたために幹の中央部が大きな穴になり、その周囲から5本の大枝が伸びています。また、太い枝が切り落とされた痕に樹皮が盛り上がり、樹の内部が空洞なのでタコの吸盤のような、またはドーナッツをいくつも置いたような形の、ごつごつしたたくさんのこぶになっています。
このクスノキは、およそ200年前に描かれた「御鷹場切絵図」に巨樹としての姿を残していて、そのころから相当な大きさだったことがわかります。主幹の上部が失われた現在でもこの大きさですから、主幹が梢まで存在したときはどのような大きさだったかと惜しまれます。
昭和50年(1975)に刊行された「宇土半島の老樹名木」には、「中央にあった大枝が枯れたためか大穴となっている。どの枝も斜上に伸び、オオイタビが下がって異形をなしている」と、昭和45年(1970)に調査した時の樹形が記録されています。その後、樹勢の衰えが目立つようになったので、平成9年(1997)に着生して繁茂しているオオイタビの除去作業が行われ、翌年には大枝を支える支柱が立てられるなどの養生作業が行われたので、現在は以前に比べて樹勢を回復してきています。
■ピンク色の阿蘇溶結凝灰岩・馬門石
この近くに馬門石(まかどいし)の採石場があります。馬門石とは、ここ馬門でしか見られない独特のピンク色をした岩石のことで、近くを流れる網津川に川石として転がっているほか、山に入ったところの採掘場では露頭の観察ができます。およそ9万年前に阿蘇火山の大噴火によって噴出した火砕流の堆積物が、高熱と自重によって溶結してできた岩石で、阿蘇溶結凝灰岩と呼ばれるものの一種です。一般的に黒色か灰色ですが、馬門産のものはピンク色をしているため、阿蘇ピンク石とも言われます。
馬門石は独特のピンク色をしていることで珍重されます。しかし、この地域で阿蘇溶結凝灰岩は馬門石だけですから、いろいろなものに当たり前に使われています。宇土市の街中にある船場橋(市指定重要文化財)は馬門石で作られていますし、日本最古の水道施設と言われる轟水源から導かれる通水管も馬門石です。
阿蘇溶結凝灰岩は阿蘇火山から噴出した大量のガスと溶岩の火砕流が九州中部の広い範囲を覆い、高温のまま堆積して固まったものです。この火砕流は先端が山口県の宇部市や天草の島まで届いており、厚いところでは30~50メートルも堆積している大規模なものです。そして、軟らかくて加工しやすい、入手しやすい石材であることから、九州中部地域を中心に「灰石」または「阿蘇石」と呼ばれて、古代からずっと人々の生活に密着して使われてきました。中世には墓石や供養塔に多く使われ、庶民は石臼や石灯籠や間地石、ときには石風呂にまで広範囲に利用していました。
■阿蘇溶結凝灰岩を使った石造アーチ橋
大きな構造物としては、肥後の石工の名を轟かせた石造アーチ橋の材料に使われたがこの石です。美里町の霊台橋は、熊本と延岡を結ぶ日向街道が深い緑川の峡谷を渡るところに、弘化4年(1847)に架けられた県下最大の眼鏡橋です。長さ88メートル高さ16メートル幅5.5メートルで、単一アーチの眼鏡橋では日本最大で、国の重要文化財に指定されています。明治33年(1900)から県道として利用されていましたから、昭和53年(1978)に平行して新しい橋が架けられるまでは、眼鏡橋の上をバスもトラックも走っていました。
もう一つ国の重要文化財に指定されているのが、江戸時代に作られた通水石橋として有名な山都町の通潤橋です。長さ75.6メートル、高さ20.2メートル、幅6.3メートルの大きな眼鏡橋で、弘化3年(1846)の起工から安政元年(1854)の完成まで8年がかりの難工事でした。橋の本体もさることながら、鉄パイプのような材料の無い時代ですから、通水管作りが大変でした。90センチメートル角の石材に30センチメートル角の通水坑をあけて橋の上に3列に並べ、強い水圧に耐え繋ぎ目から漏水しないよういろいろな工夫をしています。また、橋よりも高い位置で取水し、橋を渡った後で水が噴き上がるサイホンの原理も利用するなど、江戸時代後期の日本土木技術の最高傑作とされています。
通潤橋そのものが素晴らしい構造物であることは誰でも認めますが、それ以上に大切な施設が、橋の前後に作られた導水路と配水路です。比較的急峻な台地の斜面にトンネルや溝を掘り、水が無くて荒れ地だった白糸台地の隅々まで水を届け、豊かな田畑を養っている水路網です。少し時間が必要ですが、ゆっくり見て回ると面白い発見がたくさんあります。この地域には、県指定の雄亀橋(おけたけばし)を始め、町指定重要文化財の眼鏡橋がいくつもあり、楽しい石橋巡りができます。
■畿内の大王の巨大な石棺に使われた馬門石
古代から最も際だっている阿蘇溶結凝灰岩の使用例は、石棺の材料に用いられたことです。3世紀末から4世紀初めに始まった古墳時代は、首長を埋葬する墓作りに異常なまでのエネルギーを費やした時代です。ところが、いくら立派に古墳に埋葬しても、木造の棺では永遠の眠りについたはずの遺体が、棺とともに腐朽してしまいます。それで石の棺が作られるようになり、それが4世紀の後半に舟形石棺の形に進化しました。舟形石棺は全国に190基ありますが、その半数以上の107基が九州に集中的に分布し、その内の101基が阿蘇溶結凝灰岩で作られています。
九州以外の地域に阿蘇溶結凝灰岩の石棺があるということは、九州で作られた石棺が運ばれたということで、この問題を解きほぐしてゆけば古代史の謎が大きく解明されることが期待できます。その製作技術や製作場所、古代の交通ルートと運輸技術、当時の文化交流やその背景にある豪族たちの政治状況までが見えてくるからです。とくに、6世紀後半の継体天皇陵とされる今城塚古墳に、ピンク色の馬門石で作られた巨大な大王の石棺が発見されたことは、衝撃的な事実でした。馬門石は、ここ馬門の特産で他には産しない岩石なので、この大王の石棺はここで採石され、遠く離れた近畿地方まで運ばれたとしか考えられないからです。
■大王の石棺実験航海
何故800キロメートル以上離れた九州の宇土半島だけに産する馬門石が大王の石棺に使われたのか、6トンを超える重さの石棺をどうやって運んだのか、その謎を解こうと現在の宇土市から大阪まで、古代船に石棺を乗せて運ぶ実験航海を実行する大プロジェクトが計画されました。この壮大な計画は、長年にわたって地元の地域おこしに取り組んできた「熊本県青年塾」をはじめとする多くの人々によって動きだしました。
まず、採石場で切り出された馬門石から継体天皇陵の今城塚古墳の石棺片をもとに復元した大王の石棺を、採石場から約1.5キロメートル(干拓前の古代には500メートル)離れた海岸まで修羅(しゅら:古代の木ぞり)で運ぶ「石棺曳き出し式」を歳の神の樟の前で行いました。そして、平成17年(2005)7月24日馬門石の石棺は、それを搬送する古代船「海王」などとともに宇土マリーナを出航し、大阪南(なん)港まで、はるか1006キロメートルの大航海が実行されたのです。漕ぎ手は下関水産大学校のカッター部の学生や長崎大学、神戸大学の学生延べ740人。宇土マリーナを埋める約2千人の盛大な見送りの中、潮谷義子熊本県知事は感動の涙を浮かべ、「多くの人の熱い思いを乗せた古代船の無事を祈る」と語りました。航海中は寄港地で多くの人たちに温かく迎えられ、交流を深めました。その航海のフィナーレが目前にせまった8月26日、漕ぎ手は最後の力を振り絞ってオールを漕ぎ、大阪南港に到着したのです。真夏の太陽の下、34日間にわたる古代のロマンへの旅はテレビ放送され、話題となりました。
その古代船は、平成18年(2006)春まで九州国立博物館に特別展示された後、地元に帰り、今は、宇土マリーナに展示されています。
■住吉神社と日本最古の灯台
網津(あみづ)川の河口の前に、現在は陸続きなっている住吉神社の島があります。島全体がこんもりと茂った社叢に覆われていて、昔からの姿を今も留め、一番高い場所に社殿が鎮座しています。延久3年(1071)に肥後国司・菊池則隆が海上安全の祈願所として、大阪の住吉神社の分霊を祀ったのが始まりという古い由緒ある神社です。祭神は底筒之男命(そこづつおのみこと)、中筒之男命(なかづつおのみこと)、表筒之男命(うわづつおのみこと)の住吉大神三柱と神宮皇后で、相殿(境内社)として菊池則隆・龍神・阿蘇明神・菊池神・稲荷明神を併祀しています。細川氏入国後、天草島原の乱の時、藩主細川忠利は出陣に当たり、武運・兵船安全の祈願をし、凱旋のあと御礼参りを行って名刀等の奉納をしました。これが藩主の住吉神社崇敬の始まりです。戦国の戦乱で失われた社殿は、第3代藩主・細川綱利が現在地に再建しました。その後、第4代藩主・宣紀は参勤交代の旅で周防灘(現山口県)を航海して嵐に遭遇し、住吉神社の加護を祈願して助かった神助に報いるため、境内に高灯籠を寄進しました。航海の安全を図るために作られた日本最古の灯台だといわれていますが、これが現在の住吉灯台の前身です。
■海苔養殖の大恩人、ドゥルー女史
この住吉神社の敷地に、イギリスの海藻学者・ドゥルー女史記念碑があります。ヨーロッパの女性科学者の碑が何故ここにあるのかと不思議に思えます。しかし、女史は熊本県の水産業で重要な位置を占めている海苔養殖の、最も基礎となる研究をしてくれた大恩人なのです。そのおかげで発展した海苔養殖業に携わる人たちが、昭和38年(1963)4月14日感謝の思いを込めて、日本一の海苔漁場である有明海を一望できる小高い丘に顕彰碑を建てました。
ドゥルー女史は、ヨーロッパのアマノリが冬には良く繁茂するのに、春から夏にかけて姿を消してしまい、冬になると忽然と現れて繁茂する不思議な現象を研究していたのです。女史は、姿が見えない夏の期間もアマノリは死に絶えたのではなく、形を変えて別の場所で生命をつないでいると考えていました。その誰も見たことがない夏のアマノリが胞子を作り、冬になって放出された胞子が発芽して冬のアマノリの形になると考えたのです。それで、形もわからない夏のアマノリが生きていそうな場所を探し続け、最後に牡蠣の殻の中に小さくなって潜り込んでいるのを発見したのです。昭和24年(1949)のことでした。しかし、ヨーロッパでは海苔を食べる習慣がありませんから、世の中のためには何の役にも立たない、自然の謎解きを楽しんでいるだけの研究でした。しかし、自然科学というものは、そのような無駄としか思えない研究の積み重ねで発展してきたのです。
ところが、日本ではアマノリは古くから食用に用いられ、江戸時代の中期には浅草川(現在の隅田川)の河口で養殖が始まった高級食材でした。そのため浅草海苔という名前が定着し、盛んに養殖されて日本人の大好物となりました。浅草方式の養殖は全国に広がって、熊本県では明治維新前から菊池川・緑川・氷川・球磨川などの河口城で行われ、重要な産業となっていました。しかし、冬に繁茂したアマノリは採取して製品にするのに、夏のアマノリの状態は全く不明のままでした。
しかし、冬に寒くなるとアマノリの胞子が泳ぎ出す場所は経験的に知っていましたから、時期になると河口近くに竹の「のりひび」をたくさん立て、どこからか湧いてくる胞子が付着するのを待ちました。ただ、胞子が泳ぎ去った後に「ひび」を立てたのでは胞子が着きませんし、立てる時期が早すぎると雑草のような役に立たない海藻の胞子が着いてしまい、アマノリの胞子が着けなくなります。いくら天気予報などを参考にしても、「海苔の種子つけ」(アマノリの胞子を付着させる行為)は全く相手任せの博打のようなところがありました。
しかし、ドゥルー女史の発見を知った熊本県水産試験場の研究者太田技師(平成19年度熊本県近代文化功労者)が海辺を探したところ、女史の研究したとおり牡蠣殻にもぐり込んでいる夏のアマノリが見つかりました。以来、それまで「ウングサ」と呼ばれ、運が良ければとれるとされてきたアマノリが、県の重要な産業となったのです。
ドゥルー女史は昭和32年(1957)突然亡くなりましたが、地元では、毎年4月14日に「ドゥルー祭」が行われ、今年で46回を数えます。
|