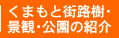|
■細川藩の財政改革の主役、ハゼノキ
このハゼノキが地元で「宝暦櫨(ほうれきはぜ)」と呼ばれるのは、宝暦4年(1754)に第6代藩主細川重賢(しげかた)公が行った藩政改革「宝暦の改革」の一つとして、水俣地区に植栽された株が現在まで生き続けて改革事業のシンボルになってきたからです。
重賢公が藩主に就任したとき、肥後藩の財政状況は極めて厳しいものでした。当時、鍋・釜・鉄瓶などの鉄製品の金気を抜く効果的な方法として、器の中に「細川様」と書いた紙を入れて一回沸騰させればよいといわれました。鍋や釜の材料がアルミなどに変わり、また表面加工の技術が進んで「金気抜き」のような処置が不要になった現代では理解されにくいのですが、新しい鉄器を洗っただけで使うと金気臭くて我慢できないものでした。それで実際に煮炊きする前に、金気が抜けるまで何回か湯炊きして、その後内側や外側についた水分をふきとるなど、手間をかけて金気を抜かなくてはなりません。それがたった一回で「細川様」が全部の金気を吸い取ってしまうから、鉄器がすぐに使えるようになるという笑い話です。
当時の細川藩は、そのような冗談話が広く流布されるほどお金がなく、あちこちに借金が溜まり現代的にいえば自己破産寸前のような状態だったのです。それを脱却するために重賢公は、大奉行に抜擢した堀平太左右衛門(ほりへいたざえもん)の下に六奉行を置く行政改革を断行し、法制改革や文教政策を次々に具体化すると同時に財政・産業政策を次々に強力に進めました。年貢米だけに依存する藩財政の限界を乗り越える新しい産業の育成に積極的に取り組んだ重賢公は、櫨蝋(はぜろう)と楮(こうぞ:和紙の材料)と生糸(きいと、絹織物の材料)の生産を藩の専売で行うことを計画しました。
産業政策のトッブに据えられた櫨蝋の事業を藩の専売として行うため設けられたのが櫨方(はぜかた)役所です。熊本市民会館前から熊本城に入る行幸橋(みゆきばし)を渡ってすぐ右に曲がり、竹の丸西枡形(ますがた)を通過した先にあるのがその役所の正門で櫨方門と呼ばれてきたものです。ただし、櫨方役所があったのは櫨方曲輪(ぐるわ)と呼ばれる現在の加藤神社が鎮座する場所で、終戦までは陸軍法務部があって西南戦争でも焼けなかった門は、その厳めしい役所の正門となっていました。戦後は県立図書館の正門となりましたが、昭和29年に白蟻の被害で倒壊寸前になって解体され、昭和32年に現在地に昔の姿のままに復元されました。
■室内照明の高級品、和蝋燭(ろうそく)の原料
ハゼノキは、ロウノキと呼ばれることもあるように、果実の皮の部分に蝋を含んでいて木蝋(もくろう)の原料とするため各地で栽培された落葉高木です。また、別名がリュウキュウハゼとかトウハゼというように、櫨蝋をとる目的で導入された外来種で、日本に自生するヤマハゼよりも多くの実をつけます。そして、それら栽培株の種子から山野に芽生えて野生化した株が増えています。身近な低山丘陵で普通に見かける木ですし、秋に美しく紅葉することと、皮膚の弱い人が枝葉に触るとかぶれることで知っている人が多い植物です。
しかし、蝋燭の原料つくりが藩の財政再建に貢献するとは考えにくいのは、現代に生きるわたしたちがエネルギーの大量使用で明るい生活に慣れすぎているからです。江戸時代の生活では、室内照明の代表は行灯(あんどん)でした。小皿に油を入れ、灯心を浸して点火し、風で吹き消されないよう障子紙を貼った枠の中に入れる、それだけの装置です。白い紙を貼った枠に入れることは、光源の面積を広くして部屋を柔らかく照らす効果もありました。とはいえ、その明るさは貧弱なもので新聞もまともに読めないくらいですので、現代のわたしたちにはとても生活できません。
江戸時代には石油系の灯油はありませんから、菜種油などの植物油を使いました。しかし、それは美味しい食用油で高価なものですから、低所得者は半額くらいで買える魚油を使っていたそうです。江戸では房総半島沖でとれるイワシの油が広く使われたといいますから、行灯を使えば部屋中に焼き魚の匂いが満ちたことでしょう。
その点、蝋燭は素晴らしく上等な照明道具です。明るくて、固体ですから持ち運びに便利で、灯明皿の油をひっくり返すような失敗もありません。でも、高価なものでしたから一般家庭ではちょっと使えない贅沢品だったのです。それで、江戸時代に人々は都市に住んで農業の現場から離れても、朝日が出れば仕事を始め夕日が沈めば家に帰って休む暮らしは変わりなかったのです。
その蝋燭はハゼノキの実を木に登って収穫し、果皮から蝋成分を圧搾または抽出して大釜で溶かし、それを日光・空気・水で晒して木蝋に仕上げてから作ります。
■各地で進められた蝋燭産業
ハゼノキは全国で植栽されましたが、もともと暖地性の植物ですから九州や四国が栽培に適した地域です。大分県の日田市は天領だったこともあって、武士の支配というより商人たちの力で豊かな町づくりがされましたが、その産業の一つが製蝋業だったのです。日田の旧家で、その屋敷建造物が大分県の文化財に指定されている草野本家では、元禄元年(1688)から電灯がともる明治の頃まで、木蝋の製造・販売を行い、京都や大阪に出していました。その折に、娘や孫のみやげに京から雛人形を持ち帰ったのが、現在の「天領日田おひなまつり」で知られる行事のもととなりました。当時雛人形はとても高価で庶民にはなかなか手に入るものではありませんでしたが、あれだけ立派な雛人形を上方から購入できたのも、櫨蝋の生産と販売が築き上げた財力の基盤があったからだったのです。ノーベル賞作家、大江健三郎の故郷、愛媛県の内子町も白壁の美しい町並みが有名で多くの人が訪れますが、ここも蝋燭産業で栄えた町です。
■ハゼノキで栄えた侍地区
それだけの経済効果が見込まれるからこそ、櫨蝋の生産が宝暦の改革における産業政策のトップにあげられたのです。その最大の拠点として水俣の小田代(おたしろ)台地の侍地区を中心に何万本ものハゼノキが次々と植えられ、栽培株数が10万本以上になったこともあります。現在でも1万5千本のハゼノキが残っていて、次々に紅葉する景観は見事です。その中の最大株が「侍の櫨」で、台風にもびくともしないくらいどっしりと根をはっています。幹は根元から分かれて力強く伸び、真下から見上げると全体が視野に収まらないほど大きく枝が広がり、樹齢250年を超える貫禄に圧倒される巨樹です。この樹からは実が240キログラムくらい採れたので、30キログラム入の俵が8個になる樹という意味で「八俵なり」と呼ばれています。
侍地区は、肥後と薩摩を結ぶ薩摩街道の国境の軍事上の要所でした。また、細川氏の直轄地であったので藩のハゼノキ栽培の拠点となったのです。集落の中心は五差路になっていて、古くは肥前陣と呼ばれ、豊臣秀吉の島津征伐の折、肥前佐賀の軍勢が陣を敷いたと伝えられます。付近には茶屋もあり、肥前茶屋といわれたそうです。この五差路にほど近い北の台地の小高いところに2枚の大きな平石が重なった「お上り石(おのぼりいし)」があります。大正2年(1913)に石の傍らに建てられた記念碑には、寛永9年(1632)初代肥後藩主細川忠利(ただとし)が藩内巡視の折、この岩に立ち境川に煙を上げさせ肥薩の国境を確認したのが先例となって代々の藩主がこれにならったことが記されています。
ここの地区は、軍事上の要所であったからか、ハゼノキの栽培事業に多くの侍が集まったからか、それとも別の由来があるのかわかりませんが、侍という面白い名前です。地元では「さむれ」とか「さむね」という言い方をしています。
「侍の櫨」に行く山道の入り口近くに「侍街道はぜのき館」があって、ハゼノキの実から精製される製品が展示され、和蝋燭作りの体験もできます。14年続いた「はぜのき祭り」が今年は中止されたのが残念です。冬になるとあちこちのハゼノキに、地域の名産「寒漬け(かんづけ)」の材料にする白い大根がたくさん掛け干しされる姿は、季節の風物詩として知られています。
■県内各地の櫨並木
熊本県は全国のハゼノキの実の生産量の30~40%を占める日本一の生産量を誇り、その中でも水俣市の生産が最大です。ただ、電灯の普及と照明器具の改良発展によって蝋燭が照明の王座から転落してしまった現在、櫨蝋の生産は非常に厳しい状態になっています。しかし、現在も趣味的な意味を含めて生産されている和蝋燭の他にも、お相撲さんの鬢付け(びんつけ)油には不可欠なものです。また、湿りが良くつやを出すため、化粧品や医薬品などさまざまな用途がある貴重な天然資源の一つです。戦前から戦後までJapan Waxの名で欧米に輸出されていたものですから、蝋燭以外の利用法の発展に期待したいものです。
ハゼノキは県内でも各地で植栽され、現在は株数が少なくなったとはいえ大津街道や御船(みふね)川堤防や菊池川堤防には櫨並木が残っています。特に「菊池川堤防の櫨並木」は平成19年2月に植物としては全国で初めて国の登録記念物に指定されました。玉名市の繁根木(はねぎ)から小浜(こばま)まで約3.7キロメートルにわたる櫨並木です。
|